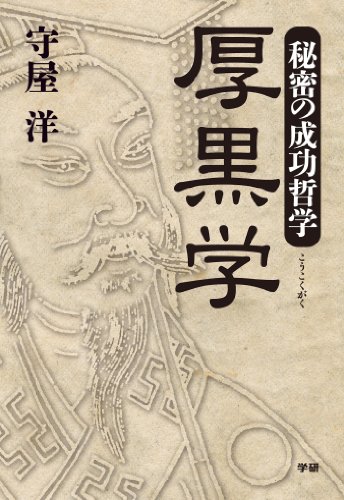1.社員に企業内テロ(?)を起こされた会社の顛末
- Ⅰ社では長年サービス残業が慢性化していた。法令で定められた従業員の労働時間の記録管理などはされておらず、労基法的には問題がある状況。これについて、労働組合も見て見ぬふりの弱腰対応。
- その結果、従業員はどれだけ遅くまで働いても残業代は出ない一方、マネジャーや役員クラスは高給をもらうという不条理。
- A氏はこの不公平さが次第に我慢できなくなり、労働基準監督署に申告することを決意。図書館で労働法関連の書籍を借りて猛勉強し、半年ほどかけて証拠書類(Ⅰ社の就業規則・給料明細・労働時間記録・臨検を求める上申書・名刺)を準備して、本店を管轄する労働基準監督署を訪れてⅠ社への臨検を要請した。労働基準監督署はA氏の持参した証拠書類から労働法違反を認定し、近日中に臨検に訪れることを確約する。
- 最初の申告日から数ケ月後に労働基準監督署の監督官が不意打ちでⅠ社を訪れて、Ⅰ社は大騒ぎ。結局、その後は紆余曲折を経て、A氏の目論見通り、Ⅰ社は労働基準監督署から行政指導を受けて労働時間の適正管理を行うことになった。
- 退職社員ではなく、現職社員からの申告ということで、労働基準監督署から是正指導があったのであろう、Ⅰ社の全従業員に対して過去6ケ月分の残業代が一斉に支払われた。A氏本人も約80万円を受け取ったとか。
- この事件をきっかけにⅠ社はこれまでのずさんな労務管理体制を改めて、全社員の労働時間をシステム管理し、1分単位で残業代を支払う方針に転換。
- その結果、Ⅰ社で慢性化していた長時間労働&サービス残業が改善されて、社員の生産性が向上したという。めでたし、めでたし(?)。

A氏は、今回の発端が労働基準監督署への申告であることを社内の誰一人にも言わず、腹に隠し持ったまま、普通に勤務しており、なかなか見上げた神経の図太さと策士ぶりを発揮。A氏によれば、「収入を増やしたい労働者にしてみれば、下手に土日に副業するよりも、単価が大きい残業代を確実に回収した方が毎月の手取りを増やすことができる。だったら、労働基準監督署という国家機関を使って会社をぶん殴った方が一番手っ取り早い」との事。なるほど、そういうものか。
2.氷河期世代の逆襲!?
このようなサービス残業という問題は、別にⅠ社に限らず、日本中の大半の会社でいくらでも転がっている話だろう。この場合、労働者側の選択肢としては、
- 我慢する(=泣き寝入りする)
- 我慢せずに労働基準監督署に申告する(=実力行使する)
の二つしかない。ただ、労働基準監督署という役所はあくまで受け身というスタンスで、労働者からの申告を受けて、確実な証拠を確認しなければ、積極的に動こうとしない。えてして国家権力とはそういうものだし、労基法違反を申告する側としては、役所が動く(=動かざるを得ない)ようにしむけるための下準備が必要になってくる。ここが最大のポイントで、ある程度の段取りと工夫が必要になってくる。
結局、A氏の行動がなければ、おそらくⅠ社は今でもサービス残業を継続していただろう。労働者を保護するべき労働組合も会社側の御用組合と化しており、まともに機能していなかった様子(A氏も最初から労働組合を全くアテにしておらず、いきなり労働基準監督署にこの話を持って行った)。今回の労働基準監督署の指導を受けて、組合の幹部連中はあわてて労働時間管理の必要性を声高に言い始めたから、これまた失笑もの。

まあ、私も会社側の立場になって考えると、この不景気の中、無制限に残業代を支払っていたら、人件費の圧迫で企業経営が立ち行かないのは十分理解できる。しかし、だからといって、物価高や税金アップがジワジワと押し寄せる厳しい状況下で暮らしている労働者としては、残業代ゼロはさすがに受け入れることはできない。

ちなみに、私とほぼ同年代のA氏は、一見すると非常にまじめなサラリーマン風で、このような大胆な事をするようには見えないから不思議。ただ、本人に言わせると「俺は『図太く、腹黒く生きる』がモットーなのさ。バブルのおいしい時代を経験していない俺たち氷河期世代が今の厳しい時代を生き抜くためには、利用できるものは何でも利用するし、したたかに行動することが大事。そもそも俺は今まで国に税金をきちんと払っているのだから、こういう時こそ自分の利益のために国家権力を合法的に活用して何が悪いねん。俺たち氷河期世代をなめるなよ!」と一喝。
・・・誠にごもっとも。今のようなサラリーマン受難の厳しい時代を生き抜くためには、これぐらいの腹黒さやしたたかさは必要。これぞリアル版「ロスジェネの逆襲」と言えばいいのだろうか。是非私もあやかりたいものだ。